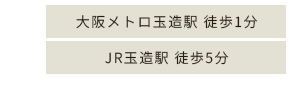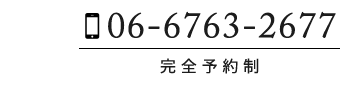五感を刺激する感触あそび~触覚編~

初めまして。
リボディ魚住の保育士です。
私が保育現場で経験、体験したことが
皆さんの子育てに少しでもお役に立てたらと思い
保育士の視点からお話していきたいと思います。
「保育士の言うことだから絶対!」ではなく
皆さんの子育てのヒントとして参考程度に
楽しく読んで頂けたらと思っています(^^)
今日のテーマは
「五感を刺激する感触あそび~触覚編~」です。
前回リボディ魚住でのイベントの様子と
小麦粉遊びの内容についてお話しました。
その中で、乳幼児の間に
五感をたくさん刺激することが
大切だとお伝えしましたが
小麦粉遊び以外にも
五感を刺激する遊びはたくさんあります。
今回は小麦粉遊び以外にできる
五感を刺激する感触あそびとして
主に触覚を刺激するあそびのアイデアを
お伝えしようと思います♪
1:癖になる感触あそび
2:「あら、不思議…」な感触あそび
3:みんなきっと1度はした!懐かしの感触あそび
癖になる感触あそび
それは・・・寒天あそびです!!
子供ってゼリーや豆腐など
プルプルした柔らかいものを
手でぐちゃぐちゃにしませんか?笑

食事中だと食事のマナーとして注意します。
しかし、子供にとっては
あの感触が好きだったり、
潰すと形が変わる何とも言えない楽しさを
味わっているのです。
その感覚を大切にして
叱られることなく遊べるのが
寒天あそびなんです!!!
では、肝心の材料と作り方です。
<材料>
・粉末寒天
・食紅
・水
・寒天を固まらせるタッパー
※牛乳パックでも可能
<作り方>
寒天を作る要領と同じです★
1.粉末寒天と食紅を
記載の容量の水と混ぜ合わせる
2.火にかけて混ぜながら粉を溶かす
3.タッパー等に入れて固める
以上。とても簡単なんです!!
冷蔵庫で冷やし固めればひんやりした
触感も楽しむことができます。
また、水の量を少なくすると
固めの寒天が出来上がるので
水の量を変えればいろんな固さの感触を
楽しむこともできますよ♪
食紅で色を付けることで
透き通ったキラキラの
宝石みたいな寒天に
子供達が注目するのは間違いなしです♡
手で握ってつぶしたり、型抜きをしたり、
夏場だとおむつやパンツ1枚になって
身体全体で潰して楽しむのも
寒天あそびの魅力です♡
「あら、不思議…」な感触あそび
次の遊びは、片栗粉粘土です!
小麦粉粘土はよく聞くと思いますが
片栗粉でも遊べるんですよ♪
小麦粉粘土は、最後は1つに固まりますが
片栗粉粘土は
1つの塊に固めることはできないんです!
まずは材料と作り方からお伝えしますね。
<材料>
・片栗粉 150g
・水 100CC
・遊べるサイズのボールや洗面用バケツなど
<作り方>
ボールやバケツ片栗粉を入れて
粉の様子をみながら
水と混ぜ合わせていくだけです。
遊び方は、まず粉だけをまず楽しみ
水を入れるとトロトロになる
変化を楽しむのがポイントです!

そして、トロトロになった片栗粉を
手でぎゅっと握ってみてください。
一瞬手の中で片栗粉が固まります。
その後、そ~っと手を開くと・・・
あら!不思議!!
手のひらの上で片栗粉が解けて
トロトロに戻るんです!!!
子供達はこの変化が
不思議でたまらなくなります♪
私も何度も遊んでますが
何度しても不思議です(笑)
片栗粉粘土は小麦粉粘土よりも
手にまとわりつきます。
なので、汚れるのが苦手なお子様は
小麦粉粘土や①の寒天あそびから始めて
汚れることに徐々に慣れることが
楽しめるようになる秘訣です!!

みんなきっと1度はした!
懐かしの感触あそび
それは、スライムです!!
懐かしくないですか?
お父さん、お母さんも
作ったことないですか?
スライムも触覚を刺激する
感触遊びの1つです!!
お父さん、お母さんも
幼少期を思い出して子供と一緒に
遊んでみてはいかがでしょうか?
スライムの材料、作り方です。
<材料>
・プラスチック製の容器(コップなど)2つ
・PVA洗濯のり 50㎖
・ほう砂 2g
・絵の具
・水 50㎖
・お湯 25㎖
・割りばし
<作り方>
プラスチック容器1つに
洗濯のり、水、絵の具を入れてかき混ぜる
2.もう1つの容器に
ほう砂にお湯を加え混ぜ合わせる
3.1に2を入れて混ぜる
以上で完成です♪
スライムは手には付きにくいですが
手触りはものすごく楽しめると思います!
ただ、スライムは薬品も使っています。
寒天あそび、片栗粉粘土に関しては
食材しか使っていないので
万が一子供が口に入れてしまっても安心ですが
スライムは遊ぶ時に子供から
目を離さないように注意してくださいね♡

いかかでしたか?
子供は日常の中でいろんな発見をしていますが
食べ物で遊ぶなど
マナーを破ってしまっていることは
ある程度の段階で注意せざる負えませんよね。
でも、普段止められることも
違うものを代用したり
「今日はOK!」の時間を作ってあげれば
子供の発見や気付きはどんどん磨かれます。
なんでもダメ!にするのではなく
今は遊びじゃない。今は遊んでいい。の
けじめをつけて楽しむことも
大切なように思います。
最後まで読んで頂きありがとうございました。